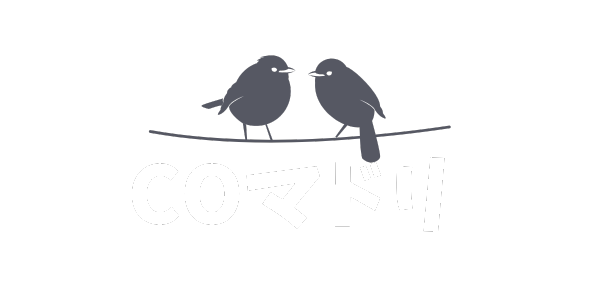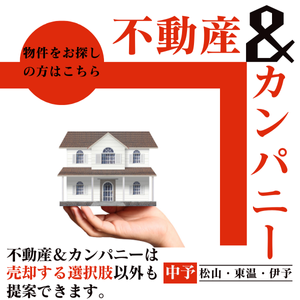流通業務市街地整備法は、不動産取引において重要な法律の一つです。
この法律は、都市部の物流効率化と交通渋滞の緩和を目的としており、流通業務施設を効率的に配置することで、物流のスムーズな運行を支援します。
具体的には、トラックターミナルや鉄道貨物駅、卸売市場、倉庫などの流通業務施設が集中している地区を「流通業務市街地」として指定し、これらの施設を一箇所に集めることで、流通機能の向上と道路交通の円滑化を図ります。
この法律は1966年に制定され、都市部の交通渋滞と物流の非効率化を解消するために導入されました。
流通業務地区は都市計画法に基づき指定され、交通要衝地に位置し、物流の効率化が期待できる地域が選ばれます。
流通業務地区内では、流通業務施設以外の建設や改築、用途変更は原則として禁止されており、例外的に許可が必要な場合もありますが、都道府県知事の承認が必要です。
不動産取引において、売買の対象となる不動産が流通業務地区内に該当する場合、重要事項説明書に記載し、制限内容を説明する必要があります。
この記事では、流通業務市街地整備法の概要とその重要性について、一般の方にもわかりやすく解説します。

流通業務市街地整備法の目的
まず、正式名称は、「流通業務市街地の整備に関する法律」といいます。
この法律の目的は、都市における流通業務市街地の整備に関する必要な事項を定めることで、流通機能の向上と道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持と向上に寄与することです。
流通業務市街地とは?
- 定義: 流通業務施設(トラックターミナル、鉄道貨物駅、卸売市場、倉庫など)が集中している地区のことをいいます。
- 目的: 流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るために、これらの施設を一箇所に集める。

流通業務市街地整備法の歴史
流通業務市街地整備法が制定された背景には、都市部における交通渋滞と物流の非効率化が深刻な問題となっていたことがあります。
1960年代、日本の経済成長に伴い、物流量が急増し、都市部ではトラックや貨物車両の増加により交通渋滞が頻発していました。
この状況は、物流の効率を低下させるだけでなく、都市生活にも大きな影響を与えていました。
特に、無秩序に立地する物流施設が都市の交通を混乱させ、効率的な物流を妨げていました。
これを解決するためには、物流施設を一箇所に集約し、効率的に運営する必要がありました。
そこで、流通業務市街地整備法が1966年に制定され、流通業務施設を集中的に配置することで、物流の効率化と交通渋滞の緩和を図ることが目指されました。
この法律により、流通業務施設が集中する地区が「流通業務市街地」として指定され、これらの地区内では流通業務施設以外の建設や改築が制限されるようになりました。
これにより、物流の効率化が進み、都市部の交通渋滞も緩和されることが期待されました。

重要事項説明における流通業務市街地整備法
まず、宅地建物取引業法施行令についてみていきます。
(宅建業法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)
宅地建物取引業法施行令第3条第1項第17号
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項
上記のとおり、「流通業務市街地整備法第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項」について重要事項説明で説明が必要になるということです。
以上3つの条文について要約すると以下の通りです。
流通業務市街地整備法第五条第1項(流通業務地区内の規制)
流通業務地区内では、特定の流通業務施設(例:トラックターミナル、卸売市場、倉庫など)以外の施設の建設、改築、用途変更は原則禁止されています。
ただし、都道府県知事が流通業務地区の機能を害さない、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合は例外です。
流通業務市街地整備法第三十七条第1項(流通業務施設の建設義務)
施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令に従って建設計画を立て、施行者の承認を受けて、その計画に基づいて流通業務施設を建設しなければなりません。
流通業務市街地整備法第三十八条第1項(造成敷地等に関する権利の処分の制限)
造成敷地等やその上に建設された流通業務施設の所有権や使用権などの権利の設定や移転については、公告の日から10年間、都道府県知事の承認が必要です。
ただし、国や地方公共団体が関与する場合や相続などの特定の条件下では例外があります。
まとめ
要するに、流通業務地区では、流通業務に関連する施設のみが建築可能です。そのため、居住用不動産の売買には流通業務市街地整備法はほとんど関係ありません。
ただ、物件調査の上で売買対象となる不動産が流通業務地区内にある場合は、上記3つの制限内容について重要事項説明で説明が必要になります。

以下にそれぞれ3つの条文を記載していますのでご参考ください。
(流通業務地区内の規制)
流通業務市街地整備法第5条第1項
第五条 何人も、流通業務地区においては、次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。ただし、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次条第一項及び第二項において「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
二 卸売市場
三 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場
四 上屋又は荷さばき場
五 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗
六 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
七 金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
八 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
九 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫
十 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場
十一 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの
(流通業務施設の建設義務)
流通業務市街地整備法第37条第1項
第三十七条 施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定める者を除く。)は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者の承認を受け、当該計画に従つて流通業務施設を建設しなければならない。
(造成敷地等に関する権利の処分の制限)
流通業務市街地整備法第38条第1項
第三十八条 第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りではない。
一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める者である場合
二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
三 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合
五 その他政令で定める場合
流通業務地区は全国のどこに指定されていますか?
ちなみに、流通業務地区は全国の主要都市や交通の要所内に指定されています。
- 京浜港周辺(東京都、神奈川県)
- 阪神港周辺(大阪府、兵庫県)
- 名古屋港周辺(愛知県)
- 博多港周辺(福岡県)
- 仙台塩釜港周辺(宮城県)
- 広島港周辺(広島県)
これらの地域は、国際物流の結節地域として重要な役割を果たしており、物流の効率化と交通渋滞の緩和を目的として流通業務地区に指定されています。

まとめ
・流通業務市街地整備法は、都市の流通機能向上と交通円滑化を目的に、流通施設を集中的に配置する法律です。
・流通業務市街地整備法は、1960年代の都市部の交通渋滞と物流の非効率化を解消するために、物流施設を集中的に配置する目的で1966年に制定されました。
・流通業務市街地整備法は、流通業務地区内での特定施設の建設・改築・用途変更を制限し、流通業務施設の建設義務と権利処分の制限を定めています。
・流通業務市街地整備法は、流通業務地区内の不動産取引において、特定の施設の建設や改築に関する制限を説明する必要があるが、居住用不動産は建築ができないため、重要事項説明で説明する機会はあまり多くはないです。
・流通業務地区は、全国の主要都市や交通の要所(京浜港、阪神港、名古屋港、博多港、仙台塩釜港、広島港)に指定され、物流効率化と交通渋滞緩和を目的としています。
以上、流通業務市街地整備法についてまとめてみました。
他にも重要事項説明で出てくる法令についてまとめていきたいと思いますのでぜひ読んでいってください。