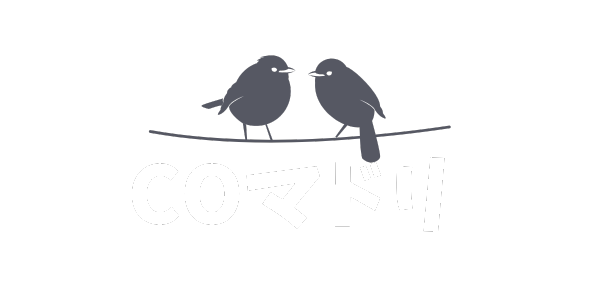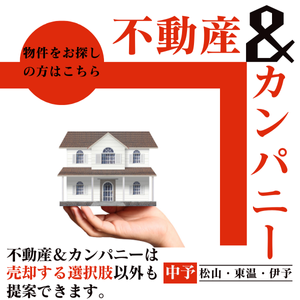こんばんわ。
コマドリです。
私たちの生活空間は、周囲の景観に大きく影響されます。
美しい景色は心を豊かにし、快適な生活環境を作り出します。
しかし、都市の発展と共に、その大切な景観が失われつつある現実に直面しています。そこで重要になってくるのが「景観法」です。
この法律は、国土の美しい景観を保全し、良好な生活環境を確保するために制定されました。
不動産を取引する際、特に重要なのがこの景観法の理解と適用です。
本記事では、景観法がどのように私たちの生活と不動産取引に影響を与えるのか、そして、その法律に違反した場合にはどのようなペナルティがあるのかを、わかりやすく解説していきます。

景観法とは何か?
景観法は、美しい国土の景観を保全し、良好な生活環境を形成するための法律です。
この法律は、特定の地域における建築物のデザインや色彩など、景観に影響を与える要素に対して規制を設けています。
景観法の制定された背景
景観法が制定された背景には、日本の都市開発と景観保全の歴史的な課題が深く関わっています。
高度経済成長期以降、日本では経済性を優先し、地域の調和や美観、伝統を軽視した建築物が全国に建設されました。
これにより、長い年月をかけて形成された伝統的な街並みや自然景観が失われ、ヨーロッパなどの国々と比較して無秩序でみすぼらしいと評される状況になりました。
また、高層マンションの建設や屋外広告の氾濫などによるトラブルが増加し、景観の価値に対する国民の意識が高まりました。
一部の地方自治体では景観条例を定めていましたが、これらは自主条例であり強制力がなく、建築確認の際に必ずしも従う必要はありませんでした。
1990年代に入ると、国土交通省も公共工事において景観への配慮を重視し始め、「美しい国づくり政策大綱」を策定しました。
これらの動きを受けて、2004年に景観法が公布され、2005年に全面施行されました。
景観法の制定は、景観を整備・保全するための国民共通の基本理念を確立し、地方公共団体に対して一定の強制力を付与することを目的としています。
これにより、地方自治体は景観計画や条例を策定し、地域住民が締結する景観協定に実効性と法的強制力を持たせることが可能になりました。
景観法は直接景観を規制するものではなく、地方自治体の計画や条例、景観協定を通じて、総合的に良好な景観形成を推進するための法的枠組みを提供しています。

景観法の目的(景観法第1条)
景観法の目的は、日本の都市や農山漁村における良好な景観を育成し、美しい国土と豊かな生活環境を創出することです。
これにより、個性的で活力のある地域社会を実現し、国民生活の質の向上と経済及び社会の健全な発展に貢献することを目指しています。
具体的には、景観計画の策定とその他の施策を通じて、この目的を達成することが法律の主旨です。
景観法の基本理念(景観法第2条)
基本理念1: 良好な景観は国民共通の資産であり、その整備と保全が必要。
基本理念2: 自然、歴史、文化との調和を重視し、適正な土地利用による景観の整備と保全を推進。
基本理念3: 地域固有の特性を尊重し、住民の意向を反映した多様な景観形成を目指す。
基本理念4: 地域間交流と観光の促進に貢献し、地域活性化に向けた一体的な取り組みを促す。
基本理念5: 既存の良好な景観の保全と新たな景観の創出を目的とする。

景観法の主要な規定
景観法における主な規制内容は以下の通りです。
- 景観計画の策定: 地方公共団体が景観計画を策定し、良好な景観の形成を促進します。
- 景観行政団体の役割: 都道府県や指定都市などの景観行政団体が、景観に関する規制内容を定めます。
- 建築物の規制: 新築・増築・改築、外観の変更などに関する規制があり、事前に届出が必要です。
- 工作物の規制: 工作物に対する形態意匠の制限や色彩の変更などが規制されています。
- 開発行為の規制: 開発行為や政令で定める行為に対する規制があります。
- 景観地区の設定: 強制力のある地域地区として景観地区が設定され、建築物の形態意匠などに関する具体的な制限があります。
- 届出制度: 景観計画区域内での行為には、事前の届出が必要であり、景観行政団体の長への届出が求められます。
- 罰則規定: 届出の未提出や虚偽の申告、勧告や変更命令に従わない場合には罰金が科されることがあります。
これらの規制は、景観法に基づいて策定された景観計画の対象となる区域や、より強制力のある地域地区として定められた景観地区で適用されます。
景観計画と景観地区の違い
「景観計画」と「景観地区」は、日本の景観法に基づく異なる概念で、以下のような違いがあります。
景観計画
地方公共団体が定める総合的な基本計画です。
良好な景観の形成のための行為の制限や景観重要建造物、景観重要樹木の指定方針などを含みます。
景観計画区域は、良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域で、市町村の全域など広範なエリアを対象にすることが多いです。
景観地区
都市計画に定められる、市街地の良好な景観の形成を図るための特定の地区です。
つまり、都市計画区域内で指定することができるということです。
景観地区では、建築物の形態意匠の制限や建築物の高さの最高限度など、より具体的な規制が可能です。
景観地区は、景観計画区域よりも小さなエリアで、強制力のある地域地区として設定されます。
これらの違いは、景観法に基づく規制の範囲と強制力の度合いに関連しています。
景観計画はより広範な規制を設けるための基盤であり、景観地区は特定の地域に対してより具体的な規制を行うための枠組みです。

不動産取引の重要事項説明で必要な条文
不動産取引の際の重要事項説明で、景観法が該当する場合で景観法の説明をする必要がある部分は、宅地建物取引業法施行令に記載があります。
(宅建業法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)
宅地建物取引業法施行令第3条第1項第7号
第3条 七
景観法第十六条第一項及び第二項、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条、第八十七条第五項並びに第九十条第四項
上記宅建業法施行令で示されている条文の内容を要約したものは以下のとおりです。
【景観法】
- 第16条第1項及び第2項(景観計画区域内での届出及び勧告等)
景観計画区域内で建築物の建築や工作物の新設等を行う場合、事前に景観行政団体の長に届出が必要。 - 第22条第1項(景観重要建築物の現状変更の規制)
景観重要建造物として指定された建築物は、増築や改築、除却、外観の変更には景観行政団体の長の許可が必要。 - 第31条第1項(景観重要樹木の現状変更の規制)
景観重要樹木の指定を受けた木に対して、伐採や移植などを行う場合、景観行政団体の長の許可が必要。 - 第41条(景観行政団体の管理協定の効力)
景観計画区域内の土地所有者は、全員の合意により景観協定を締結できる。 - 第63条第1項(景観地区内での建築計画の認定)
景観地区内で建築物の建築等を行う場合、市町村長の認定が必要。 - 第72条第1項(景観地区内での工作物の形態意匠等の制限)
景観地区内の工作物について、市町村は条例で形態意匠の制限などを定めることができる - 第73条第1項(景観地区内での開発行為等の制限)
景観地区内での開発行為等に関する制限を市町村が条例で定めることができる。 - 第75条第1項及び第2項(準景観地区内における建築行為の規制)
準景観地区における建築物や工作物の規制基準、開発行為等の制限を市町村が条例で定めることができる。 - 第76条第1項(地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限)
地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限を市町村が条例で定めることができる。 - 第86条(景観行政団体の景観協定の効力)
景観協定に関する一般的な規定。 - 第87条第5項(景観協定の認可の公告のあった後、景観協定に加わる手続等)
景観協定の変更や解除に関する規定。 - 第90条第4項(一の所有者による景観協定の設定)
単一所有者の土地に設定された景観協定が、後に複数所有者が出現しても3年以内であれば同じ効力を持つと規定。
上記のとおり、対象条文数が多いですが、
主に、「第16条第1項、第2項」「第63条第1項」が実務上、比較的多いと思います。
簡単にいうと、16条は指定地区内で建築行為を行う場合には届出が必要であること、63条では建築予定の建築物に対する行政の認定を受けないといけないというものです。
実際の重要事項説明では、建築時にはこのような届け出もしくは認定を受ける必要がでてくることの説明が必要になってきます。

景観法違反時のペナルティ
景観法には罰則が設けられています。
景観法では、事前相談や届け出の時点で勧告や変更命令が行われますが、すでに建てられた建築物があった場合は、条例違反になることがあります。
景観条例などに違反していた場合は、原状回復命令が出されたり、工事の施工の停止、改築、修繕、色彩変更、模様替えなどの是正措置が取られることがあります。
また、景観法における罰則として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
これは違反行為によって定められており、法律に基づく具体的な規制を無視した場合に適用される可能性があります。
勧告に従わない場合、罰則は直接適用されませんが、高さ制限以外の項目について勧告に従わなかった場合は、直ちに設計変更等の命令を行います。
命令違反に対しては、景観法の規定に基づく罰金等の罰則があります。
具体的な罰則内容
景観法の罰則規定について以下要約してまとめています。
- 第101条: 命令違反に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
- 第102条: 以下様々な命令違反や申請書の不正提出に対して、50万円以下の罰金。
1. 命令違反
2. 申請書未提出・虚偽提出
3. 建築工事違反
4. 応急仮設建築物の不正存続 - 第103条: 以下届出や報告の不正、立入検査拒否などに対して、30万円以下の罰金。
1. 届出未提出・虚偽届出
2. 報告未提出・虚偽報告
3. 立入検査拒否
4. 届出行為着手違反
5. 行為違反
6. 許可条件違反
7. 命令違反
8. 認定表示違反 - 第104条: 上記102条、103条の違反行為については、法人や代表者に対しても罰金刑を科す。
- 第105条: 景観行政団体の長の命令違反に対して、30万円以下の過料。
- 第106条: 報告未提出・虚偽報告に対して、20万円以下の過料。
- 第107条: 届出未提出・虚偽届出に対して、5万円以下の過料。
- 第108条: 条例違反に対して、50万円以下の罰金の規定設定可能とする。
これらの罰則は、景観法の目的である良好な景観の形成と保全を促進し、違反行為に対して一定の抑止力を持たせるために設けられています。
景観法に従い、適切な手続きを踏むことが重要です。
景観計画と、景観地区の調べ方
景観計画については、「(自治体名) 景観計画」と調べれば大体はインターネット上でその区域内がどこになるのか、について調べることができます。
景観地区については、指定されている地域が限定的です。
全国で36都市で指定されており、日本で景観地区に指定されている主な地域をあげてみます。
- 鎌倉市(神奈川県): 歴史的風土や自然景観と融和したまちなみを保持するための地区
- 京都市(京都府): 伝統的な街並みや自然を背景に持つ美観地区。
- 倉敷市美観地区(岡山県): 伝統的な町並みが残る地区。
- 尾道市景観地区(広島県): 瀬戸内海に面した歴史的な町並みを有する地区。
- 石垣市(沖縄県): 自然豊かな景観を保持するための地区。
他にも、兵庫県、大阪府、広島県などでも地域地区の指定地域があります。
※国土交通省HPの、令和4年度都市交通調査・都市計画調査より。
つまり、該当する都市であれば、「(自治体名) 景観地区」で調べれば、検索に引っかかると思いますので、気になる方は調べてみてください。
すぐにわかる場所でいえば、国土交通省HPの都市交通調査・都市計画調査のところで調べることができますのでご参考ください。。

まとめ
・景観法は、日本の美しい国土と豊かな生活環境を守り育てるために、景観計画の策定と保全を通じて地域社会の活性化と国民生活の向上を目指す法律です。
・景観法は、地方公共団体による景観計画の策定と強制力のある景観地区の設定を通じて、建築物や工作物の規制を行い、違反には罰金を科すことで、良好な景観の形成を促進する法律です。
・景観計画は地方公共団体による広範囲の基本計画であり、景観地区は都市計画によるより具体的な規制を行う小規模な地域です。
・不動産取引における重要事項説明では、主に、景観法に基づく建築行為の届出や市町村長の認定が必要な点を説明することが求められます。
・景観法違反には勧告や命令に従わない場合の是正措置や、具体的な規制違反に対して1年以下の懲役または50万円以下の罰金などのペナルティが設けられています。
以上、景観法についてまとめてみました。
他にも重要事項説明で出てくる法令について、記事をまとめていますのでご参考ください。