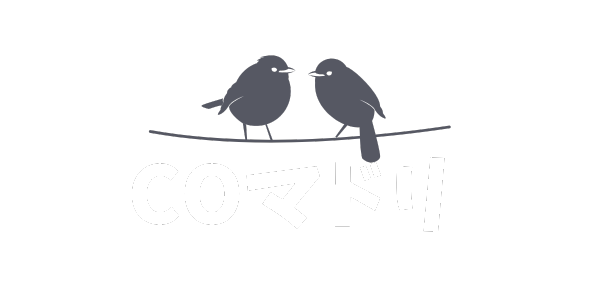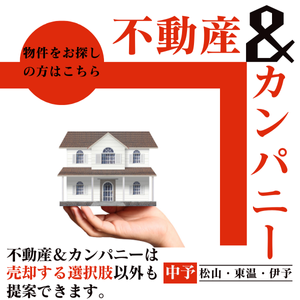こんにちわ。
コマドリです。
都市の発展とともに、古い市街地の再生と改善は重要な課題となっています。
特に、駅前広場やその周辺の高度利用を図るためには、適切な法律と施策が必要です。
そこで登場するのが「旧市街地改造法」です。
この法律は、1961年に制定され、老朽化した市街地の再生を目的としていました。
駅前広場を中心とした市街地整備や、その周辺部の建築物と敷地の高度利用を推進するために、多くの施策が講じられました。
しかし、1969年に都市再開発法が制定されたことで、旧市街地改造法は廃止されました。
それでもなお、この法律の影響は現在も一部で残っており、不動産取引における重要事項説明書にも関連しています。
本記事では、旧市街地改造法の概要やその歴史、そして現代における影響について詳しく解説します。
都市の再生と発展に興味がある方や、不動産取引に関わる方にとって、理解を深める一助となることでしょう。

旧市街地改造法とは
概要
旧市街地改善法は、正式には「公共施設の整備に関する市街地の改造に関する法律」といい、1961年(昭和36年)に制定されました。
この法律は、駅前広場を中心とする市街地整備とその周辺部の高度利用を図るために作られました。
目的は、老朽化した建物やインフラの改善を通じて、都市の魅力を高め、住みやすい環境を提供することです。
歴史と廃止
旧市街地改善法は、都市の再生と活性化を目指して多くの施策を実施しましたが、1969年(昭和44年)に都市再開発法が制定されたことで廃止されました。
しかし、当時施行されていた防災建築街区造成事業は、そのまま効力を持ち続けています。
現代への影響
現在でも、不動産取引における重要事項説明書には、旧市街地改善法に基づく制限が記載されることがあります。
特に、防災建築街区内での土地の形質変更や建築物の建築には、国土交通大臣や都道府県知事の許可が必要です。

不動産の重要事項説明書における「旧市街地改造法」とは?
不動産の重要事項説明書における「旧市街地改造法」とは、
1969年(昭和44年)に都市再開発法の制定により廃止されましたが、それに代わる都市再開発法が制定されました。
但し、この法律の施行時の1969年6月14日時点で施行されていた防災建築街区造成事業については、そのまま効力を持ちます。
そのため、不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において、
【旧市街地改造法(旧防災建築街区造成法において準用する場合に限る。)】
とされています。
防災建築街区造成事業とは、建設大臣(現国土交通大臣)が関係市町村の申出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの、または防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区を防災建築街区とし、この街区において行う防災建築物やその敷地の整備に関する事業です。
防災建築街区内で事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の建築などの行為をしようとする場合は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
このように、旧市街地改造法は廃止された法律ですが、特定の条件下での防災建築街区造成事業に関連して、現在も不動産取引における重要事項説明書に影響を与えており、重要事項説明でもこの防災建築街区に該当する不動産の場合には説明義務が必要と宅地建物取引業法施行令にも明記されております。
(宅建業法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)
宅地建物取引業法施行令第3条第1項第14号
十四 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合に限る。)
(建築行為等の制限)
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項
第十三条 都市計画事業として決定された市街地改造事業を施行すべき土地の区域内において、市街地改造事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事(建設大臣が市街地改造事業を施行すべき土地の区域内にあつては、建設大臣。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。

防災建築街区造成事業とは
事業の目的と背景
防災建築街区造成事業の主な目的は、災害に強い都市づくりを推進することです。
日本は地震や台風などの自然災害が頻発する国であり、都市部においても災害リスクが高い地域が存在します。
特に、老朽化した建物が密集する旧市街地では、火災や地震による被害が大きくなる可能性があります。
こうした背景から、防災建築街区造成事業は、災害リスクを低減し、安全で快適な住環境を提供するために重要な役割を果たしています。
事業の内容
防災建築街区造成事業では、以下のような施策が実施されます。
- 耐火建築物の整備:
- 防災建築街区内では、耐火性能の高い建物の建設が推奨されます。これにより、火災発生時の延焼リスクを低減し、住民の安全を確保します。
- インフラ整備:
- 道路や上下水道などのインフラ整備も重要な要素です。災害時に迅速な避難や救援活動が行えるよう、道路の拡幅や耐震化が進められます。
- 土地利用の最適化:
- 防災建築街区内では、土地の利用計画が見直され、災害リスクを考慮した土地利用が推進されます。例えば、避難場所の確保や防災施設の設置が行われます。
防災建築街区内での行為制限
防災建築街区内では、災害リスクを低減し、安全な都市環境を維持するために、特定の行為に対して制限が設けられています。
これらの制限は、計画的な防災対策を実施し、住民の安全を確保するために重要です。
土地の形質変更
防災建築街区内で土地の形質を変更する場合、例えば土地の掘削や盛土などの行為には、国土交通大臣や都道府県知事の許可が必要です。
これにより、土地の安定性が確保され、災害時の地盤崩壊などのリスクを防ぎます。
建築物の建築
新たに建築物を建てる場合や既存の建築物を改築・増築する場合も、同様に許可が必要です。
特に、耐火性能や耐震性能が求められる建築物については、厳格な基準が適用されます。
これにより、火災や地震発生時の被害を最小限に抑えることができます。
その他の行為
防災建築街区内では、その他にも以下のような行為が制限されることがあります:
- 大規模な土地利用変更
- 高層建築物の建設
- 特定の産業活動の実施
これらの行為制限は、地域の防災計画に基づいて設定されており、住民の安全と都市の持続可能な発展を両立させるために不可欠です。
許可の取得手続き
行為制限に該当する場合、事前に関係当局に申請し、許可を取得する必要があります。
申請には、行為の詳細や防災対策に関する計画書を提出することが求められます。
許可を得ずに行為を行った場合、法律に基づき是正措置が求められることがあります。

旧市街地改造法が適用されている都市はあるの?
いくつかあります。
例で言えば、
埼玉県さいたま市浦和駅前
東京都港区新橋駅前
神奈川県横浜市鶴見駅西口
などなどです。
参考に、各自治体のHPのリンクを張っておりますのでご参考ください。
旧市街地改造法が適用されいている部分には、「※市街地改造事業」等とわかるように書かれています。
まとめ
・旧市街地改造法は、1961年に制定され、老朽化した市街地の再生を目的とした法律で、1969年に廃止されたが、防災建築街区造成事業は現在も効力を持ち、不動産取引に影響を与えています。
・不動産の重要事項説明書における「旧市街地改造法」とは、1969年に廃止されたが、防災建築街区造成事業は現在も効力を持ち、不動産取引において説明義務がある法律です。
・防災建築街区造成事業は、災害リスクの高い地域で耐火建築物やインフラ整備を行い、安全な都市環境を維持するために、特定の行為に対して許可が必要な施策です。
・旧市街地改造法が適用されている都市には、埼玉県さいたま市浦和駅前や東京都港区新橋駅前、神奈川県横浜市鶴見駅西口などがあります。
以上、「旧市街地改造法」についてまとめてみました。
要するに、旧市街地改造法については今でも適用される場所は存在しており、これも限定的ですが、同法に基づく規制がかかる不動産はあるということです。
ただ、ほとんどお目にかかることはないような法令にはなるため、もし気になる方は、各自治体で調べてみて、今後の参考にしてください。