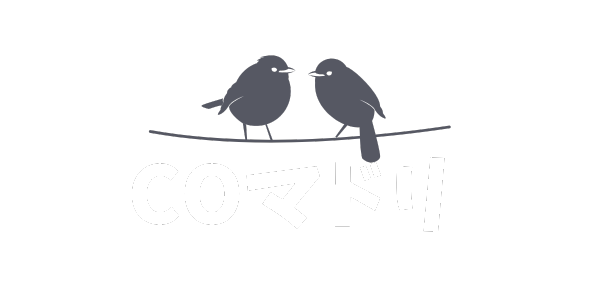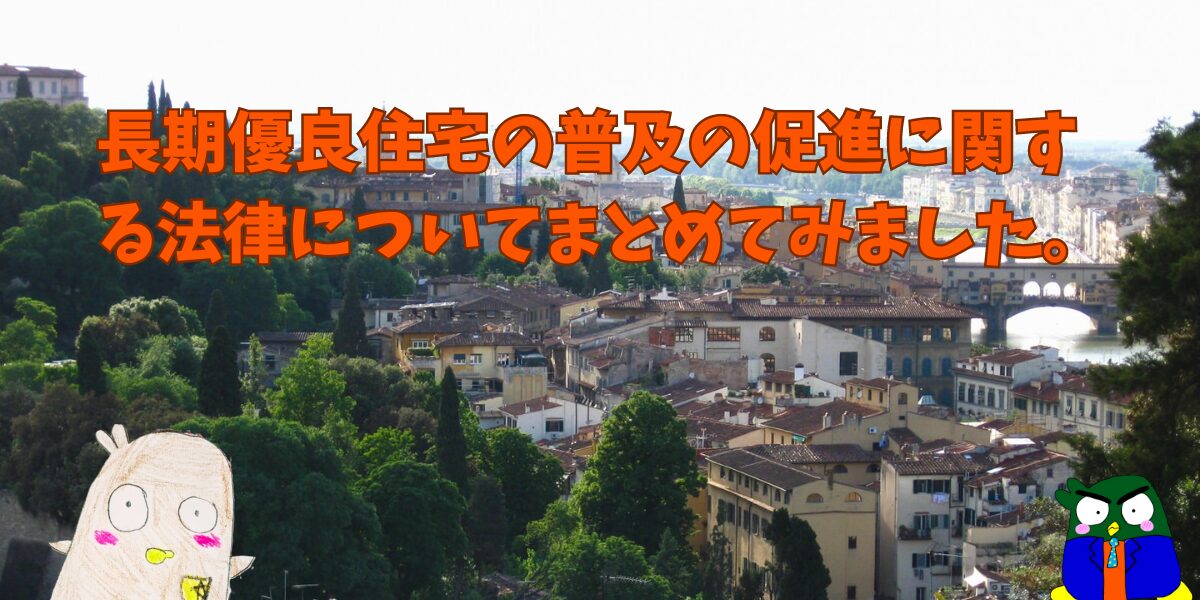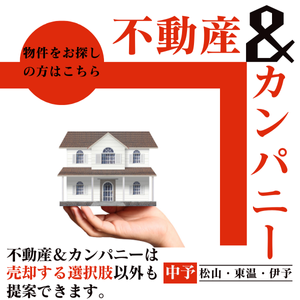こんにちは。
コマドリです。
住宅の購入や建築を考えている方にとって、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は重要なポイントです。
この法律は、長期間にわたり良好な状態で使用できる住宅の普及を目指しており、環境負荷の低減や資産価値の維持に大きく貢献します。
本記事では、長期優良住宅の定義や基準、重要事項説明ではどのような内容の説明義務があるのか、について解説します。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは?
- 法律の目的:長期にわたり良好な状態で使用できる住宅の普及を促進するための法律。
- 施行日:2009年6月4日。
- 背景:住宅の質を向上させ、環境負荷を低減するために制定。
(目的)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第1条
第一条 この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。
重要事項説明ではどの部分の説明が必要?
購入予定の不動産が、「長期優良住宅」だった場合に、重要事項説明では説明が義務づけられていますが、それでは具体的にはどの部分が説明が必要なのか?を確認していきます。
まず、説明義務内容が規定されている宅地建物取引業法施行令第3条第1項を見ていきます。
二十九 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項
とあり、上記の条文も合わせてみていきます。
(容積率の特例)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第18条第1項
第十八条 その敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、同法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
この条文をもう少し簡潔にまとめてみます。
容積率の特例(第18条第1項)
- 対象:政令で定める規模以上の敷地面積を持つ住宅。
- 条件:認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築。
- 許可要件:
- 交通上、安全上、防火上、衛生上の支障がないこと。
- 建蔽率、容積率、高さについて総合的な配慮がなされていること。
- 市街地の環境整備改善に寄与すること。
- 特例内容:特定行政庁の許可を得た場合、建築基準法の容積率の限度を超えることができる。
「政令で定める規模以上の敷地面積」とは、具体的には以下のとおりです。
(容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)
| 地域または区域 | 敷地面積 |
|---|---|
| 第1種(第2種)低層住居専用地域 田園住居地域、指定のない区域 | 1,000㎡ |
| 第1種(第2種)中高層住居専用地域 第1種(第2種)住居地域 準住居地域、準工業地域 工業地域、工業専用地域 | 500㎡ |
| 近隣商業地域、商業地域 | 300㎡ |
以上の内容の説明が、不動産取引における重要事項説明で義務とされています。
ただ、一般的に、敷地面積基準が大きすぎるため、あまりこの容積率特例が適用される案件は少ないと思われます。
そのあたりのことも踏まえて、重要事項説明で説明すればよりわかりやすく話が入ってきやすいと思います。
まとめ
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、良質な住宅の普及を促進し、住生活の向上と環境負荷の低減を図ることを目的としています。
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第18条第1項では、特定行政庁の許可を得た場合、一定の条件下で容積率の限度を超えることができると規定しています。
・重要事項説明では、長期優良住宅の容積率の特例に関する説明が必要で、具体的には敷地面積の規模や特定行政庁の許可条件について説明する必要があります。
以上、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は重要事項説明ではどのような内容の説明が必要かについてまとめてみました。
他にも重要事項説明で出てくる法令でどのような内容の説明が必要か、記事にしていますのでご一読ください。