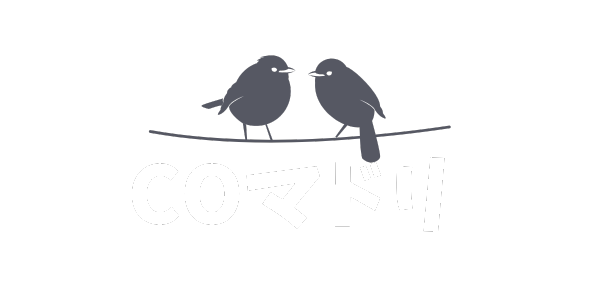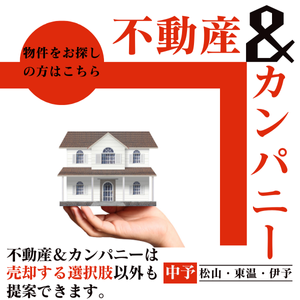こんにちわ。
コマドリです。
都市部の緑地は、私たちの生活にとって欠かせない要素です。
しかし、都市化の進展により、これらの貴重な緑地が失われつつあります。
そこで重要な役割を果たすのが「都市緑地法」です。
この記事では、都市緑地法がどのように私たちの緑地を守り、都市生活を豊かにしているのかを、わかりやすく解説します。
緑豊かな都市を守るための法律の知識を深め、より良い都市環境づくりに役立てましょう。
また、不動産取引における重要事項説明でも、この都市緑地法については説明を行う必要が出てきます。
その説明が必要な内容は何なのか、解説していきたいと思います。

都市緑地法とは?
都市緑地法は、昭和48年に作られ、平成29年に改正されており、都市部における緑地の保全と緑化を推進するための法律です。
この法律は、良好な都市環境を形成し、健康で文化的な都市生活を確保することを目的としています。
都市緑地法の制定された背景
都市緑地法の制定背景は、以下の通りです。
- 都市化の進行: 都市部の発展に伴い、緑地が減少し、生活環境の悪化が懸念されました。
- 環境保護の必要性: 健康で文化的な都市生活を確保するため、自然環境の保全が重要視されるようになりました。
- 災害時の安全確保: 緑地は災害時の避難場所としても機能するため、その確保が求められました。
- 気候変動対策: 気候変動への対応として、都市部の緑地の質と量の確保が必要とされています。
- 生物多様性の確保: 生物多様性の保持には、都市部における緑地の維持が不可欠です。
- 市民の福祉向上: 市民の幸福度を高めるため、緑豊かな環境の提供が重要とされています。
これらの背景に基づき、都市緑地法は、都市部における緑地の保全と緑化を推進し、良好な都市環境の形成を図ることを目的として制定されました。
この法律は、都市公園法とともに、都市における自然的環境の整備を目的とする重要な法律となっています。

都市緑地法における規制区域及び規制内容
緑地保全地域
緑地保全区域に関する内容は以下の通りです。
- 緑地保全地域内の届出義務(都市緑地法第8条第1項): 特別緑地保全地区および一部の地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除き、緑地保全地域内で建築物の新築、土地の形質変更、木竹の伐採などの行為を行う場合、事前に都道府県知事へ届け出る必要がある。★重説でのポイント
- 都道府県知事の権限: 都道府県知事は、緑地保全地域内で届け出が必要な行為に対して、緑地保全のために必要と認められる場合、行為を禁止または制限することができる。
- 届出後の処分期間: 届け出をした者に対しては、届け出日から30日以内に処分を行うことができる。
- 処分期間の延長: 必要がある場合、都道府県知事は処分期間を延長し、その旨を届け出者に通知する。
- 行為の着手制限: 届け出をした者は、届け出日から30日経過後でなければ行為に着手できない。
- 期間の短縮: 緑地保全に支障がないと認められる場合、都道府県知事は着手制限期間を短縮できる。
- 国の機関や地方公共団体の例外: 国の機関や地方公共団体が行う行為には届け出が不要で、代わりに通知が必要。
- 通知後の協議: 通知があった場合、都道府県知事は緑地保全のための措置について協議を求めることができる。
- 特定行為の適用除外: 公益性が高い事業、既に着手していた行為、非常災害時の応急措置など、特定の行為には届け出や通知の規定が適用されない。
これらの要約は、緑地保全地域内での行為に関する届け出義務や、都道府県知事の権限、行為の着手に関する制限など、都市緑地法第八条の主要な内容を説明しています。
特別緑地保全地区
都市緑地法第十四条に関する要約は以下の通りです。
- 特別緑地保全地区内の行為制限(都市緑地法第14条第1項): 特別緑地保全地区内での建築物の新築、土地の形質変更、木竹の伐採などの行為には、都道府県知事の許可が必要。★重説でのポイント
- 許可の例外: 公益性が高い事業、既に着手していた行為、非常災害時の応急措置など、特定の行為は許可の必要がない。
- 許可申請の審査: 都道府県知事は、申請された行為が緑地保全に支障があると認める場合、許可を出してはならない。
- 許可条件: 必要がある場合、都道府県知事は許可に期限や条件を付けることができる。
- 通知義務: 特定の行為を行う者は、事前に都道府県知事に通知する必要がある。
- 届出義務: 既に行為に着手している者や非常災害時の行為をした者は、指定された期間内に都道府県知事に届け出る必要がある。
- 助言や勧告: 都道府県知事は、必要があると認める場合、通知や届出をした者に対して助言や勧告をすることができる。
- 国の機関や地方公共団体の行為: 国の機関や地方公共団体が行う行為には許可が不要だが、協議が必要。
- 適用除外の行為: 特定の計画に基づく行為や通常の管理行為など、一部の行為は規定の適用がない。
これらの要約は、特別緑地保全地区内での行為に関する届け出義務や、都道府県知事の権限、行為の着手に関する制限など、都市緑地法第十四条の主要な内容を説明しています。
指定地域の所有者であるメリットもあります。
特別緑地保全地区の指定には土地所有者にとって次のようなメリットがあります。
次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
- 相続税:山林及び原野については8割評価減となります。
- 固定資産税が最大1/2まで減免されます。
- 建築行為等の申請が不許可となった時に、行政への土地の買入れを申し出ることができます(都市緑地法第17条)。譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。
- 管理協定制度を併用することにより、管理の負担を軽減することができます。
- 市民緑地制度を併用することにより地域の自然とのふれあいの場として活用を図ることができます。

緑化地域
緑化地域についての詳細は以下の通りです。
- 都市計画による指定: 緑化地域は都市計画によって定められる地域地区の一つです。
- 緑地不足の解消: 良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している区域に指定されます。
- 緑化の推進: 建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域に適用されます。
- 緑化率の義務: 一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合、敷地面積の一定割合以上の緑化が義務付けられます。★重説でのポイント
- 緑化施設の定義: 緑化施設には植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木などが含まれます。
- 緑化率の最低限度: 都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度を満たすことが求められます。
- 適用除外: 学校など特定の用途や敷地の状況によってやむを得ないと認められる建築物は適用除外となる場合があります。
これらの要約は、都市緑地法における緑化地域の設定、緑化率の最低限度の定義、違反建築物に対する措置、報告及び立入検査に関する規定を説明しています。
緑地協定
緑地協定についての詳細は以下の通りです。
- 合意に基づく制度: 緑地協定は、土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。
- 地域環境の改善: 地域住民の協力により、街を良好な環境にすることが目的です。
- 協定の種類: 全員協定(45条協定)と一人協定(54条協定)の2種類があります。
- 全員協定: 既にコミュニティが形成されている市街地で、土地所有者等全員の合意により締結されます。
- 一人協定: 開発事業者が分譲前に協定を定め、後に複数の土地所有者が存在することになった場合に効力を発揮します。
- 協定の内容: 緑地協定では、緑地の区域、緑化に関する事項(樹木の種類や場所、構造物など)、有効期間、違反時の措置などを定めます。★重説でのポイント
- 助成措置: 市町村によっては緑地協定の締結に対して助成措置を設けている場合があります。
これらの点は、都市緑地法に基づき、地域の緑地を保全し、良好な環境を維持するための協力体制を築くための重要な法的枠組みを提供します。
市民緑地
市民緑地についての詳細は以下の通りです。
この内容は、法令に該当していなくても重説での説明義務はない内容となります。
ただ、都市緑地法には法令として明記されているため、参考までにご確認ください。
- 定義: 市民緑地は、民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができる制度によって設置された緑地施設です。
- 目的: 都市に残された貴重な民有地の緑を保全し、地域に憩いの場を提供することを目的としています。
- 認定制度: 地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度です。
- 対象要件: 緑化地域または緑化重点地区内で、周辺地域で良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している場合に対象となります。
- 面積と緑化率: 認定される市民緑地は、面積が300平方メートル以上で、緑化率が20%以上である必要があります。
- 設置管理期間: 認定された市民緑地は、5年以上の期間、設置・管理されることが求められます。
- 支援措置: 固定資産税や都市計画税の軽減など、税制上の支援措置が設けられている場合があります。
これらの情報は、市民緑地が都市環境における緑地の確保と公共の利用を促進するための重要な制度であることを示しています。

重要事項説明での説明ポイント
重要事項説明で説明が必要なポイントは以下のとおりです。
まずは、宅地建物取引業法施行令を見ていきます。
(宅地建物取引業法 第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)
宅地建物取引業法施行令第3条第4号 (一部記号等付け加えています)
四 都市緑地法 ①第八条第一項、②第十四条第一項、③第二十条第一項、④第二十九条、⑤第三十五条第一項、⑥第二項及び第四項、⑦第三十六条、⑧第三十九条第一項、⑨第五十条、第五十一条第五項並びに⑩第五十四条第四項
以上の都市緑地法の条文に該当する場合、重要事項説明で説明が必要となります。
それぞれの条文について、それぞれ内容をみていきましょう。
都市緑地法に定める以下の規制区域とその規制内容は以下の通りです。
緑地保全区域の重要事項説明部分
都市緑地法第8条第1項
緑地保全地域における行為の届出等に関する都市緑地法第八条第1項に基づく要約は以下の通りです。
- 緑地保全地域内での届け出義務: 特別緑地保全地区や一部の地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除き、緑地保全地域内で以下の行為を行う場合、事前に都道府県知事へ届け出る必要がある。
- 新築・改築・増築: 建築物や工作物の新築、改築、増築。
- 土地の形質変更: 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採など。
- 伐採: 木竹の伐採。
- 水面の変更: 水面の埋立てや干拓。
- その他影響行為: 緑地の保全に影響を及ぼすおそれのあるその他の行為。
これらの行為は、緑地の保全に直接関わるため、法律によって厳しく規制されています。
特別緑地保全地域の重要事項説明部分
都市緑地法第14条第1項
特別緑地保全地区における行為の制限に関する都市緑地法第十四条に関する要約は以下の通りです。
- 特別緑地保全地区内の行為制限: 特別緑地保全地区内での特定の行為には、都道府県知事の許可が必要。
- 建築制限: 新築、改築、増築などの建築活動。
- 土地形質変更制限: 宅地造成、土地開墾、土石採取、鉱物掘採など。
- 伐採制限: 木竹の伐採。
- 水面変更制限: 水面の埋立てや干拓。
- その他影響行為: 緑地保全に影響を及ぼすその他の行為。
ただし、公益性が高く緑地保全に支障がないと認められる事業、既に着手していた行為、非常災害時の応急措置については、許可が不要です。
この条文は、特別緑地保全地区内の緑地を守るための重要な規制を定めております。
都市緑地法第20条第1項
地区計画等緑地保全条例に関する都市緑地法第二十条第1項の要約は以下の通りです。
- 地区計画等緑地保全条例の目的: 市町村は、地区計画等の区域内で良好な居住環境を確保するため、現存する樹林地や草地などの緑地の保全に関する事項を定めることができる。
- 特別緑地保全地区の除外: 特別緑地保全地区はこの条例の適用から除かれる。
- 市町村長の許可: 地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内で、第十四条第一項に掲げる行為を行うには市町村長の許可が必要。
この条文は、市町村が地区計画に基づいて緑地の保全を図るための規制を設けることができることを示しており、特定の行為を行う前に市町村長の許可が必要とされています。

管理協定(所有者と自治体や緑化保全法人との協定)の重要事項説明部分
都市緑地法第29条
管理協定の効力に関する都市緑地法第二十九条の要約は以下の通りです。
- 管理協定の公告後の効力: 第二十七条の規定による管理協定が公告された後、その管理協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、管理協定の効力が及ぶ。
この条文は、管理協定が公告された後に土地の所有者が変わった場合でも、新しい所有者は管理協定の内容を遵守しなければならないことを明確にしています。
これにより、緑地の管理と保全が一貫して行われることを保証しています。
緑化地域の重要事項説明部分
都市緑地法第35条第1項、第2項及び第4項
緑化率に関する都市緑地法第三十五条第1項、第2項、第4項に関する要約は以下の通りです。
- 緑化率の最低限度: 緑化地域内で政令で定める規模以上の建築物を新築または増築する場合、都市計画で定められた緑化率の最低限度を満たさなければならない。
- 適用除外: 周囲に広い緑地を有し、都市環境に支障がないと認められる建築物、学校など特定の用途で必要と認められる建築物、崖地など特定の地形にある建築物は、市町村長の許可により緑化率の規定の適用から除外されることがある。
- 敷地が複数区域にわたる場合: 建築物の敷地が緑化率に関する制限が異なる複数の区域にわたる場合、緑化率は各区域の最低限度を基に計算される。
この要約は、緑化地域内での建築活動における緑化率に関する法的要件を簡潔に説明しており、特に、建築物の新築や増築を行う際には、都市計画に定められた緑化率の基準を遵守する必要があり、一部の建築物については市町村長の許可により例外が認められることが示されています。
また、敷地が複数の区域にまたがる場合の緑化率の計算方法についても言及されています。
都市緑地法第36条
一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例に関する都市緑地法第三十六条に関する要約は以下の通りです。
- 一団地の緑化率規制: 建築基準法に基づき一の敷地とみなされる一団地や一定の一団の土地にある建築物に対しては、その一団地や区域全体を一つの敷地とみなし、前条(第三十五条)の緑化率の規定を適用する。
この条文は、複数の建築物がある一団地や一定の区域について、それらを一つの敷地として扱い、緑化率の計算を行う際にはその全体を基準とすることを定めています。
これにより、一団地内の緑化率を適切に管理し、都市環境の緑化を促進することが目的です。

地区計画等緑化率条例の重要事項説明部分
都市緑地法第39条第1項
地区計画等の区域内における緑化率規制に関する都市緑地法第三十九条第1項に関する要約は以下の通りです。
- 地区計画等の緑化率規制: 市町村は、地区計画等の区域内で定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で新築または増築される建築物、およびその建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
- 適用区域の限定: この規制は、地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、または沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限られる。
この要約は、市町村が地区計画に基づいて建築物の緑化率に関する最低限度を設けることができること、およびその適用が特定の計画によって定められた区域に限られることを示しています。
緑地協定の重要事項説明部分
都市緑地法第50条
緑地協定の効力に関する都市緑地法第五十条の要約は以下の通りです。
- 緑地協定の公告後の効力: 第四十七条第二項の規定による認可が公告された緑地協定は、公告後に緑地協定区域内の土地所有者となった者に対しても効力を有する。
- 例外: ただし、緑地協定に合意しなかった者が所有する土地の所有権を承継した者はこの効力の適用を受けない。
この要約は、緑地協定が一度公告されると、その区域内で土地の所有者が変わった場合でも、新しい所有者は協定の内容に従う必要があることを示しています。
これにより、緑地の管理と保全が一貫して行われることを保証しています。
ただし、元の所有者が協定に合意していなかった場合、その土地を承継した者は協定の効力を受けません。
都市緑地法第51第5項
緑地協定の認可の公告のあった後、緑地協定に加わる手続等に関する都市緑地法第五十条第五項の要約は以下の通りです。
- 緑地協定の効力の及ぶ範囲: 緑地協定に加わった者が所有する、または借地権等を有する緑地協定区域内の土地について、緑地協定の公告後に土地所有者等となった者にも緑地協定の効力が及ぶ。
- 例外: 緑地協定に合意しなかった者が所有する土地の所有権を承継した者や、前条の規定の適用がある者は、この効力の適用を受けない。
この要約は、緑地協定が一度公告されると、その区域内で土地の所有者が変わった場合でも、新しい所有者は協定の内容に従う必要があることを示しています。
ただし、元の所有者が協定に合意していなかった場合、その土地を承継した者は協定の効力を受けません。
少し第50条と似た内容に見えると思いますので補足します。
下記の引用した第51条第1項を見ると、「緑地協定の効力が及ばないもの」が認可の広告後に、所定の手続きを踏んで緑地協定に加わった場合のその後のことを条文に明記しています。
(緑地協定の認可の公告のあつた後緑地協定に加わる手続等)
第五十一条
緑地協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑地協定の効力が及ばないものは、第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該緑地協定に加わることができる。
都市緑地法第54条第4項
緑地協定の設定の特則に関する都市緑地法第五十条第四項の要約は以下の通りです。
- 緑地協定の特則: 認可を受けた緑地協定は、認可日から3年以内に緑地協定区域内に2以上の土地所有者等が存在するようになった場合、公告された緑地協定と同じ効力を持つ。
この要約は、緑地協定が特定の条件下で公告された協定と同様の法的効力を持つことを示しています。
以上のことから、緑地協定に該当する場合、緑地協定が締結されているかどうか確認し、該当する場合に締結内容と、協定に合意した所有者から継承したらその協定も合意したことを引き継ぐ旨を伝える必要があるということを説明する必要があるということです。

まとめ
・都市緑地法は、都市部の緑地を保全し、良好な都市環境を維持するための法律です。
・届け出・許可の必要性: 特別緑地保全地区や緑化地域内で建築や土地開発を行う際は、事前に関連する届け出や許可が必要です。
・緑化率の遵守:その 新築や増築を行う場合、緑化地域における緑化率の最低限度を守る必要があります。
・緑地協定の影響: 緑地協定による規制がある地域では、その内容を理解し遵守することが重要です。
・市民緑地の活用: 市民緑地制度を利用する際は、設置・管理に関する規定や支援措置を確認することが必要です。
・法的変更のチェック: 都市緑地法は変更されることがあるため、最新の情報を定期的にチェックすることが推奨されます。
以上、都市緑地法についてまとめてみました。
他にも不動産取引における重要事項説明で説明必要箇所についてまとめていますので、他の記事もご参考ください。